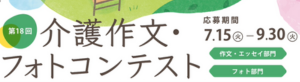福祉施設SX
-
全国施設最前線

第22回 福岡県 社会福祉法人 北筑前福祉会 デイサービスセンター 菜々
社会福祉法人 北筑前福祉会 デイサービスセンター 菜々 「共生」を理念に掲げ、1972年に法人設立。現在、福岡県内にて22事業所を運営。うち、デイサービスセンター菜々は、認知症対応型の通所介護施設として1995年に開設。地域の方々との関わり・交流を積極的に行っている 選ばれる認知症デイ…
-
特集

軽費老人ホームが抱える 課題と打開策 PART.02
目印となるキャラクターを活用し 高めた発信力で経営を後押し 多くの社会福祉法人が、地域の中で存在感をアピールすることが求められている今、軽費老人ホームも例外ではありません。むしろ、不可欠なセーフティネットとして、長い間、当たり前のように地域の高齢者を支えてきただけに、その存在に日の目が当たること…
-
特集

軽費老人ホームが抱える 課題と打開策 PART.01
経済的な理由や身体的な不安から自宅での生活が困難になった高齢者に、比較的低額な費用で住まいと生活支援を提供する軽費老人ホーム。介護が必要になる前の段階から入居でき、食事付きの集合住宅としての機能をもっています。しかし、制度の複雑さ、財政的な課題、そして社会的な認知度の低さという三重の困難に直面し、…
-
特集
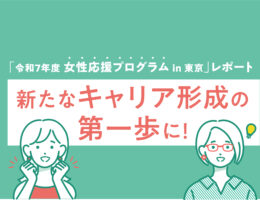
「令和7年度 女性応援プログラム in 東京」レポート 新たなキャリア形成の第一歩に!
令和7年11月17日に全国老施協女性キャリアアップ推進委員会が主催する「女性応援プログラム in 東京」が開催されました。リーダーを目指す方や興味のある方、キャリア形成に悩む方に対し、“自分らしいリーダー像とは何か”を考えることを通じて、今後のキャリア形成のヒントや目標を得てもらうことが目的。グル…
-
特集

JSフェスティバルin山口 フォトレポート
2025年12月4日(木)・5日(金)、山口市のKDDI維新ホールと山口グランドホテルにおいて「第4回 全国老人福祉施設大会・研究会議 〜JSフェスティバル in 山口〜」が開催されました。テーマは「介護最前線、新しい介護の創造と未来への挑戦」。人口減少と人材不足という現実を踏まえ、全国から2,0…
-
特集

大山知子会長 新年のごあいさつ
あきらめずに声を上げ続ける姿勢が 少しずつ形になりはじめた2025年 昨年は政府要職者との接触を積極的に重ね、介護現場の実情を訴え続けてきました。石破内閣が骨太の方針を策定される前の重要な時期に、公定価格の見直しや賃金アップ、経済スライドに合わせた制度改革の必要性を総理に直接訴え、そ…
-
全国施設最前線

第21回 石川県 社会福祉法人 福寿会 特別養護老人ホーム 福寿園
社会福祉法人 福寿会 特別養護老人ホーム 福寿園 開設は1983年。2009年に従来型からユニット型に転換し、尊厳の保持を基本とするケアをいっそう実践。「身体拘束廃止宣言」を施設全体で掲げ、人権および尊厳の尊重とQOL(生活の質)の向上を目指す取り組みを行っている 介護職による栄養管理…
キャリアアップ
-
介護現場 あるある掲示板
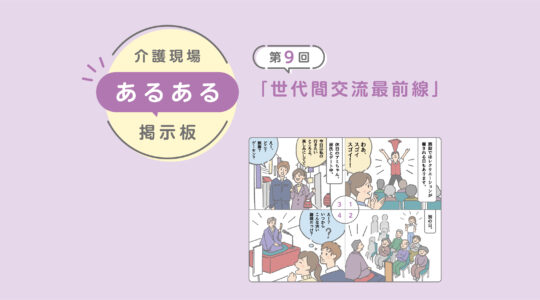
第9回 「世代間交流最前線」
第9回 「世代間交流最前線」 福祉科で学んでいる高校生に、将来なぜ介護士になりたいのかを尋ねたところ、「お年寄りと話すことで知識が増え、世界が広がるから」という答えが返ってきました。家庭で祖父母から話を聞く機会が少なくなっている若い人が多い今、何十人もの高齢者と交流できる施設は、知識の宝庫です。実…
-
介護のかくしん
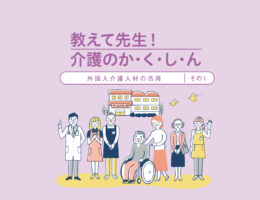
外国人介護人材の活用 その1 受入れ前の準備
介護の現場に必要な「革新」や「確信」や 「核心」をその分野の専門家にうかがいます。 日本語能力を重視することが 介護業界の大きな特徴 日本で働く外国人がますます増加する中、介護業界でも今後、より多くの外国人介護人材を採用する必要があります。ここでポイントになるのが、受入れにあたり高い日本語要件が設…
-
介護現場 あるある掲示板
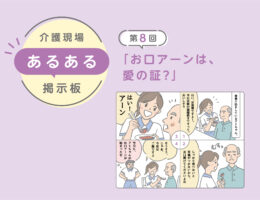
第8回 「お口アーンは、愛の証?」
第8回 「お口アーンは、愛の証?」 誰かにものを食べさせようと思うときに、思わず自分の口も開いてしまう。これは心理学では同調効果とかミラーリング効果といわれる現象で、まるで鏡のように相手のしぐさや行動を自然と真似してしまう行為と定義されています。 ミラーリングは、相手との心の距離を縮めたり、好感…
-
介護のかくしん

介護施設のマニュアル作り 「排泄ケアマニュアル」 作成の実践ガイド その2 : 手順書編
介護の現場に必要な「革新」や「確信」や 「核心」をその分野の専門家にうかがいます。 ひとつ一つの手順を確実に実施する 意味も理解してもらえる手順書に 実際のやり方やノウハウを解説する手順書は、現場で実際に使えるものでなければなりません。どこからか借りてきた理想的な手順書が、自施設の実情と乖離してい…
-
介護のかくしん

介護施設のマニュアル作り 「排泄ケアマニュアル」 作成の実践ガイド その1 : マニュアル編
介護の現場に必要な「革新」や「確信」や 「核心」をその分野の専門家にうかがいます。 介助の技術だけでなくご利用者の 心のケアの仕方もマニュアルに 食事、入浴、排泄という三大介助の中でも、ご利用者の尊厳や羞恥心にも強く関わるのが排泄介助です。排泄介助のためのよいマニュアル作りができれば、それは施設に…
-
介護現場 あるある掲示板
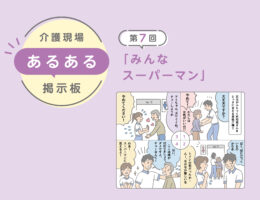
第7回 「みんなスーパーマン」
第7回 「みんなスーパーマン」 介護現場でのハラスメントは、相手の方にまったく悪意や自覚がないことも多いのですが、度重なると職員のモチベーションが下がります。 今回の例のように女性のご利用者から介助を断られて、男性職員が歯がゆい思いをすることもありますが、そんな時は女性職員に代わってもらったり、…
-
介護現場 あるある掲示板

第6回 「介護人生・生涯現役」
第6回 「介護人生・生涯現役」 介護の仕事は、長く続けられることが魅力のひとつ。年を重ねるほどにご利用者の気持ちに寄り添えるようになるから、年齢は必ずしもハンディキャップになりません。また介護は多職種で支える仕事だから、看護職員、ケアマネジャー、生活相談員、機能訓練士、調理スタッフ、事務員など、も…
こころとからだ
-
こころの橋わたし
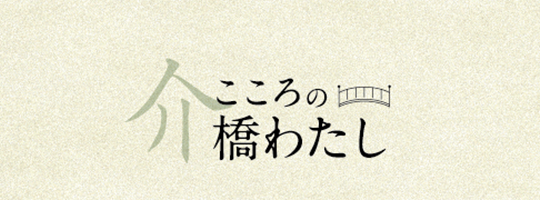
〈お悩み 22〉若いスタッフが意見を言うと すぐに遮って 否定する上長がいます。 結局、誰も意見を 言わないようになり、 介護の質の向上も望めません。
「介」という字には「間でとりもつ」「たすける」という意味があります。 尊いお仕事をされている皆さまのこころとこころをつなぐヒントになれば幸いです。 お悩み 若いスタッフが意見を言うと すぐに遮って 否定する上長がいます。 結局、誰も意見を 言わないように…
-
こころの橋わたし
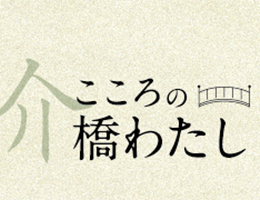
〈お悩み 21〉ちょっとしたことにすぐに腹が立ちます。我に返って後悔するもののすぐにまたヒートアップ。穏やかな心が保てません。
「介」という字には「間でとりもつ」「たすける」という意味があります。 尊いお仕事をされている皆さまのこころとこころをつなぐヒントになれば幸いです。 お悩み ちょっとしたことにすぐに腹が立ちます。 我に返って後悔するもののすぐにまたヒートアップ。 穏やかな…
-
こころの橋わたし
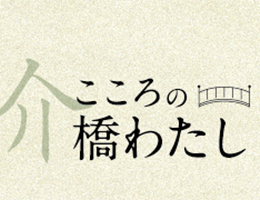
〈お悩み 20〉施設長が入社1年目の男性職員を「うちのホープ! 僕の後継者候補」と持ち上げます。それを聞いている先輩職員の寂しげな顔が気になります。
「介」という字には「間でとりもつ」「たすける」という意味があります。 尊いお仕事をされている皆さまのこころとこころをつなぐヒントになれば幸いです。 お悩み 施設長が入社1年目の男性職員を 「うちのホープ! 僕の後継者候補」と持ち上げます。 それを聞いてい…
-
こころの橋わたし
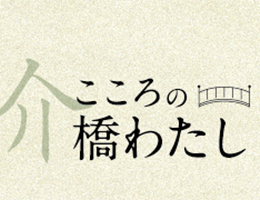
〈お悩み 19〉入職5年目の正社員です。 40歳のパート介護士さんは 私が若いことを理由に 聞く耳をもたず、 接し方に悩んでしまいます。
「介」という字には「間でとりもつ」「たすける」という意味があります。 尊いお仕事をされている皆さまのこころとこころをつなぐヒントになれば幸いです。 お悩み 入職5年目の正社員です。 40歳のパート介護士さんは私が若いことを理由に 聞く耳をもたず、接し方に…
-
こころの橋わたし
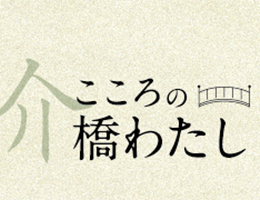
〈お悩み 18〉苦手な同僚と二人きりの 夜勤は会話も続かないので 思考も停止気味。 大事な申し送りさえ おざなりになっていそうで 不安です。
「介」という字には「間でとりもつ」「たすける」という意味があります。 尊いお仕事をされている皆さまのこころとこころをつなぐヒントになれば幸いです。 お悩み 苦手な同僚と二人きりの夜勤は 会話も続かないので 思考も停止気味。 大事な申し送りさえ おざなりに…
-
こころの橋わたし
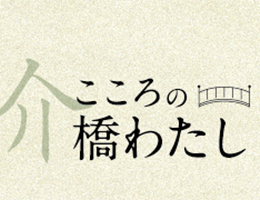
〈お悩み 17〉仲良しだったご利用者さんが亡くなり、ショックを受けてしまいました。 仕方ないことだとはわかっていても自分の無力感のようなものに苛まれます。
「介」という字には「間でとりもつ」「たすける」という意味があります。 尊いお仕事をされている皆さまのこころとこころをつなぐヒントになれば幸いです。 お悩み 仲良しだったご利用者さんが亡くなり、 ショックを受けてしまいました。 仕方ないことだとはわかってい…
-
こころの橋わたし
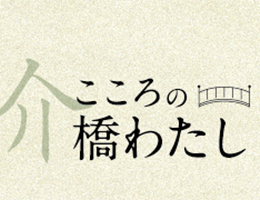
〈お悩み 16〉「がんばらなくてもいい」 という上長の真意が つかめません。 私はもっとがんばりたいのに 上長は何をもって 言ってくれたのでしょう。
「介」という字には「間でとりもつ」「たすける」という意味があります。 尊いお仕事をされている皆さまのこころとこころをつなぐヒントになれば幸いです。 お悩み 「がんばらなくてもいい」 という上長の真意が つかめません。 私はもっとがんばりたいのに 上長は何…
アーカイブ
-
介護のグルメ

春のレモンちらしずし
暖かくなってきて春を感じるこの季節にぴったりなちらしずしを紹介。レモン汁&蜂蜜を使用したすし飯はマイルドで食べやすく、サーモンと錦糸卵、菜の花といった食材の華やかさが目を奪います。 華やかで春の訪れを感じさせるちらしずしフルーティーな酸味が食欲をかき立てる! レモン汁&蜂蜜を使ったフルーティーなすし…
-
日本全国注目施設探訪

第24回 福岡県北九州市 社会福祉法人援助会 デイサービス 聖ヨゼフの園
独自の取り組みでキラリと光る各地の高齢者福祉施設へおじゃまします!※「第1回全国老人福祉施設大会・研究会議〜JSフェスティバル in 栃木〜」入賞施設を取材しています 利用者とスタッフが一緒に料理をすることで、認知症ケアに実績あり キリスト教シスターたちの活動を受け継いだ老舗施設 九州の北端にある…
-
介護現場NOW

ポストコロナの介護人材確保について考える③ 外国人介護人材に日本で活躍してもらうためには?
人材不足に苦しむ介護業界に外国人活用は必要不可欠外国人材の日本語教育を充実させ、日本永住を図るべき 外国人介護人材に対してのニーズや期待は高まっている 日本の介護業界での外国人活用は、年々増加の傾向にある。’19年に導入された在留資格「特定技能」で働く外国人が急増しているが、̵…
-
みんなの気持ち

第24回 “みんなの気持ち”を大切にするには、どのように接すればいいのでしょうか?
健康社会学者として活動する河合 薫さんが、介護現場で忙しく働く皆さんへ、自分らしく働き、自分らしく生きるヒントを贈ります。 あちらの気持ちを立てればこちらの気持ちが立たぬ あちらを立てればこちらが立たぬ、双方立てれば身が立たぬ、と古くから言われる通り、対立する両者を丸く収めるのは至難の業。うまくま…
-
特集(制度関連)

第16回介護作文・フォトコンテスト結果発表!! 〜笑顔が増える、幸せも増える〜②
第16回を迎えた介護作文・フォトコンテスト。コロナ禍前の生活に戻りつつある現在、福祉介護施設においてもおじいちゃん、おばあちゃんと「会う」「話す」機会はさらに増えていく。会って話すことで、おじいちゃん、おばあちゃんの笑顔を増やして、もっと幸せを感じてほしい、そんな思いを込めたテーマは、「笑顔が増える…
-
特集(制度関連)

第16回介護作文・フォトコンテスト結果発表!! 〜笑顔が増える、幸せも増える〜①
第16回を迎えた介護作文・フォトコンテスト。コロナ禍前の生活に戻りつつある現在、福祉介護施設においてもおじいちゃん、おばあちゃんと「会う」「話す」機会はさらに増えていく。会って話すことで、おじいちゃん、おばあちゃんの笑顔を増やして、もっと幸せを感じてほしい、そんな思いを込めたテーマは、「笑顔が増える…
-
チームのことば

【INTERVIEW】東北大学 スマート・エイジング学際重点研究センター 加齢医学研究所 応用脳科学分野 助教・博士(生命科学) オガワ淑水
今回は高齢者の暮らしの質を上げるための新たな方策を、ヨーロッパの大学・研究機関などと共同で開発している東北大学の助教・博士(生命科学)のオガワ淑水博士を、同学内の加齢医学研究所に尋ねた。このプロジェクトは、「e-ViTA(EU-Japan Virtual Coach For Smart Ageing…