福祉施設SX
いま、介護を学ぶ人たち3 高校生(福祉科)
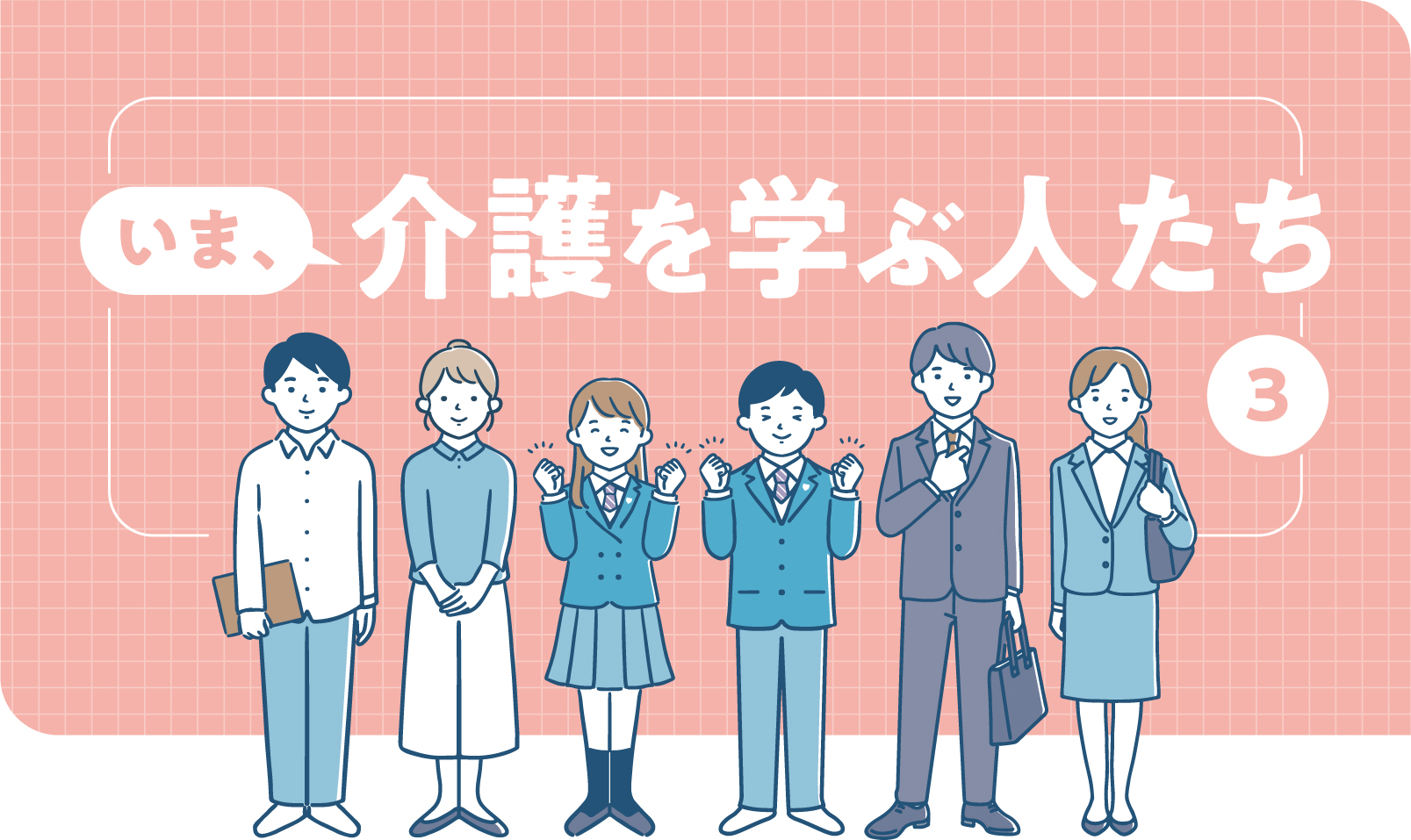
2040年に向けて介護人材の不足が懸念されているなか、少子化が進んでいることもあり、そもそも介護を学ぶ若い人たちの絶対数も減少しています。しかし、そんななかでも介護の仕事に高く関心を抱き、やりがいを求めて学んでいる学生や生徒がいます。こうした人たちの思いをくみ、いかに育てて、活躍の場を与えられるかどうかが、これからの施設の存続にも大きく関わっているのではないでしょうか。今回は「介護業界の希望」ともいえる意識の高い学生・生徒のインタビューを紹介し、こうした声に鑑みつつ、いかにして介護人材を増やせるか、そのための課題と展望を専門家が検証します。
働くならご利用者との距離が近い施設
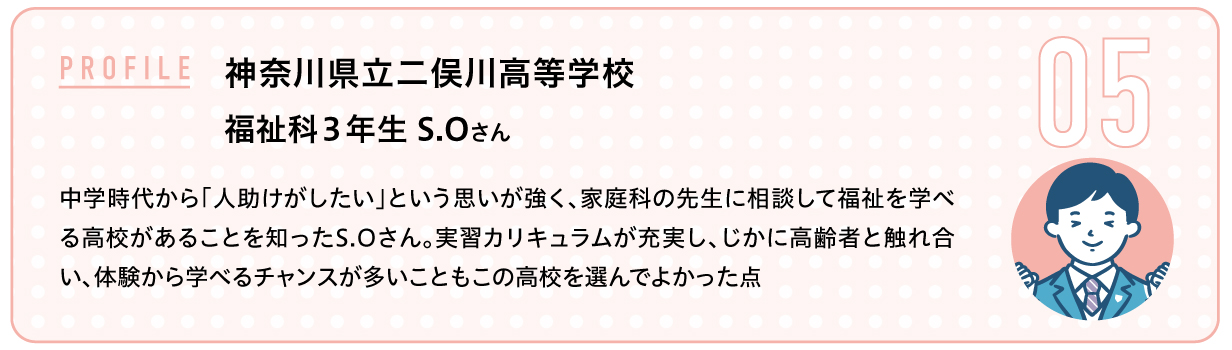
お年寄りと話すことで 広がる自分の世界
小さい頃から人と話すのが好きで、特にお年寄りと話すのが楽しくてたまりませんでした。今思うのは、介護の仕事の魅力は「お年寄りと話すことで、知らないことを知ることができ、世界が広がる」ところ。違う時代を生きてきて、自分が経験したこともない体験をしてきた方々からお話を聞くのはすごく楽しいです。だから今、進路に迷っている友人には「介護の仕事は自分自身の知識が広がるからいいよ」と勧めています。
ご利用者にも支えられて 成立している介護実習
高校では迷わず「介護実習」の授業を選択しました。その理由は介護には実践的な経験が何より重要だと考えたからです。自分の学んだことを生かしたり、新たな発見があったりするといいなと、実習の前はいつもワクワク・ドキドキしています。
そして実際に行ってみると、人と話すことが大好きな僕でも、1年生のときは初めての方と話すことにとても緊張しました。そんなとき、実習先の介護士の方から、ご利用者さんに質問をするときは「はい」「いいえ」で答えられる質問をしてはダメで、サイコロの目のようにいろいろな方向に転がしていける質問をするようにと教えてもらい、なるほどと思いました。自分たちの実習は施設の職員の方々だけでなく、ご利用者さんにも支えられて初めて成立していることがわかり、心から感謝しています。
「ありがとう」の言葉を たくさん聞けたら最高!
実習が好きなのは、少しでも多くの高齢者の方と関わりたいから、というのもあります。だから就職するなら、「ご利用者さんとの距離が近い施設」を選びたいと思い、今、ホームページで施設のことを調べるときも、まず「理念」を読んで、ご利用者さんとの距離感を確認します。
例えばケアが画一的だったり機械的だったりする施設ではなく、みんながリラックスできて、ワイワイガヤガヤにぎやかで、近くにいるお年寄りからの「ありがとう」という言葉をたくさん聞けるようなら最高です! そんな施設で長く働きたいと思っています。
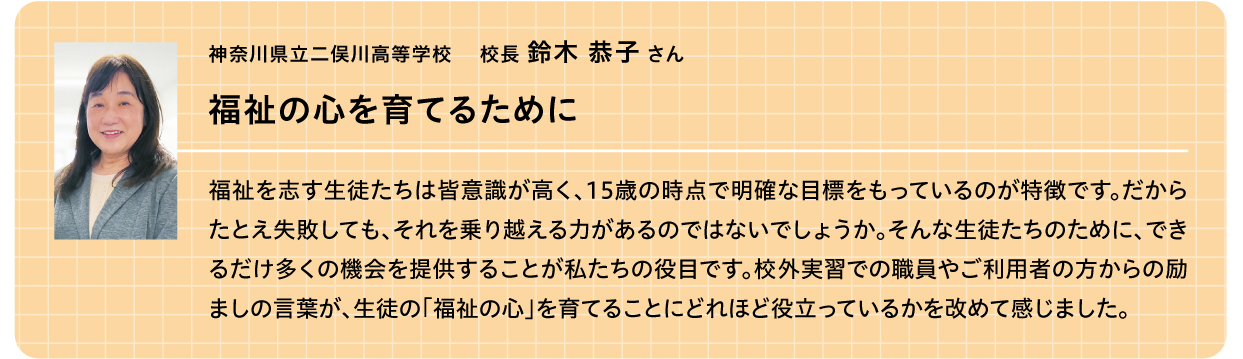
施設に求めるのは「地域」との関わり
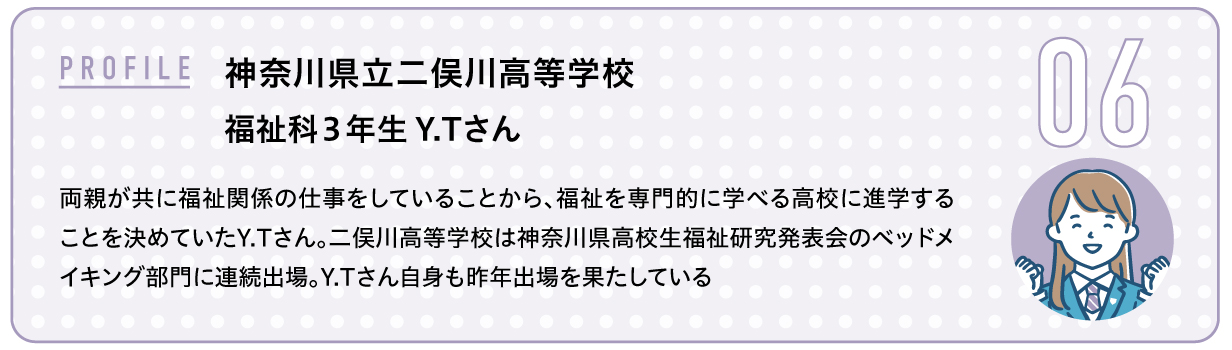
ご利用者を笑顔にする 父の姿を見て自分の進路を決定
小学生のときに父が働いている特別養護老人ホームに一緒に行く機会があったのですが、父がご利用者の方々と仲良く話し、皆さんが笑顔になっている姿を見て、社会のなかですごく役割のある仕事なのだと感じました。私自身が実際に家のなかで介護体験をしたことはないのですが、介護を専門的に学びたいという思いをあたため続け、迷うことなくこの学校を選びました。
特養での実習を通して 介護の仕事の意義を実感
実習のための施設が充実しているのも、この高校を選んだ理由です。特に特別養護老人ホームでの実習を通じて介護の楽しさやご利用者さんとの関わりを体験し、この仕事の意義を実感できました。「福祉は人生に触れられる貴重な機会なのだ」と思うようになり、ベッドメイキングなどの技術の習得にも力が入りました。実習では緊張してしまって、上手に話せないこともあるのですが、自分とコミュニケーションをとってくださっているご利用者さんを笑顔にできたらいいなと思いました。 卒業後は進学して、介護福祉士の資格を取得したいです。資格を取るために勉強することが、ご利用者さんによりよい介護を提供することにつながるのではないかと思うからです。
高齢者の生活の場である施設は いかに地域と関われるかが重要
今、介護施設のホームページを見るときには、まず理念を調べ、その理念のなかに「地域」という言葉が入っているかどうかを調べます。特別養護老人ホームなどはご利用者さんにとっては生活の場なので、そこに閉じこもってばかりいるのは悲しいし、寂しい気がします。だから単に「地域」という言葉が書かれていればよいのではなく、どう地域と関わっているのか具体的なことが書かれているとうれしくなります。将来はそんな施設で働きたいと思います。
今、さまざまな施設に実習に行くと、それぞれにフロアの作り、レクリエーション内容、食事内容、ベッドメイキングの方法などに違いがあるのが面白いと思いました。若いうちはさまざまな施設で働いて、いろいろなやり方を学んでみたいです。
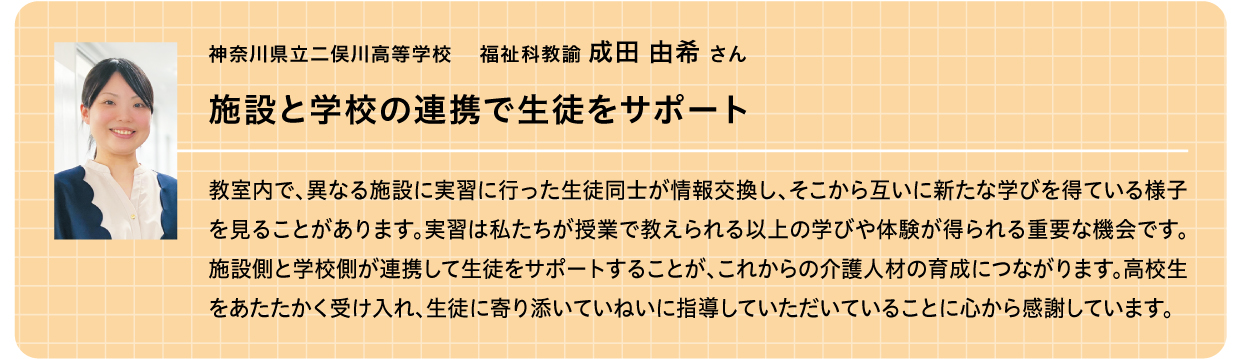
次回は「介護人材の確保と育成に関する課題と展望」について、鈴木俊文教授(静岡県立大学)のお話です。
取材・文=池田佳寿子
