福祉施設SX
第3回全国老人福祉施設大会・研究会議 JSフェスティバル in 滋賀 誌上レポート 専門家による先駆的特別報告
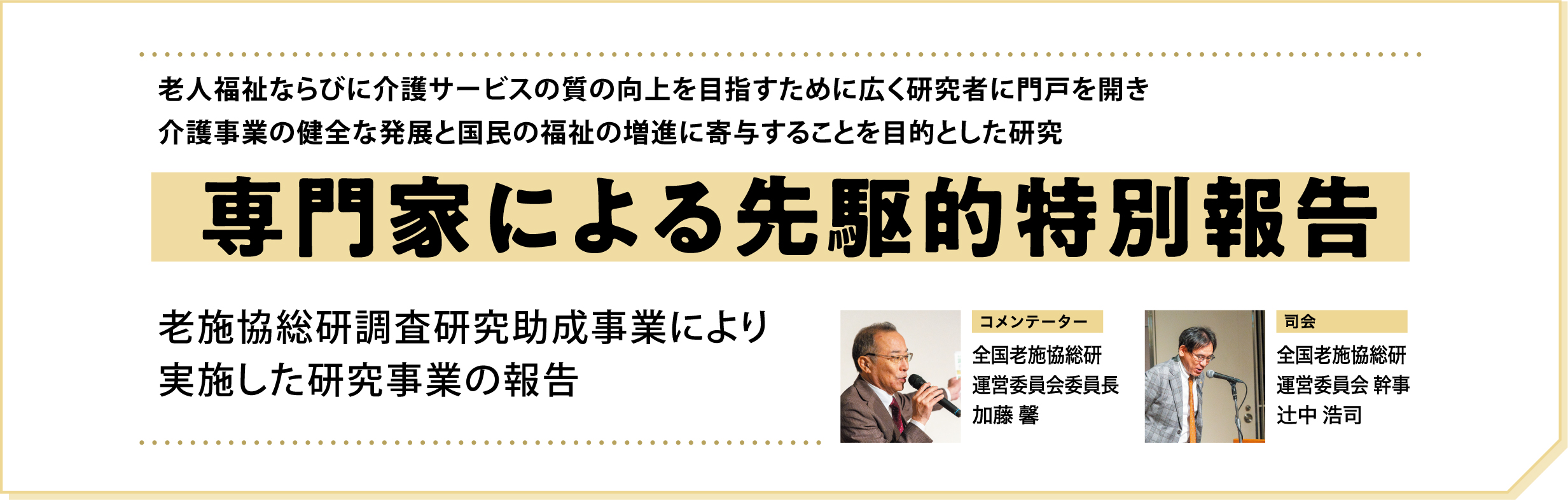
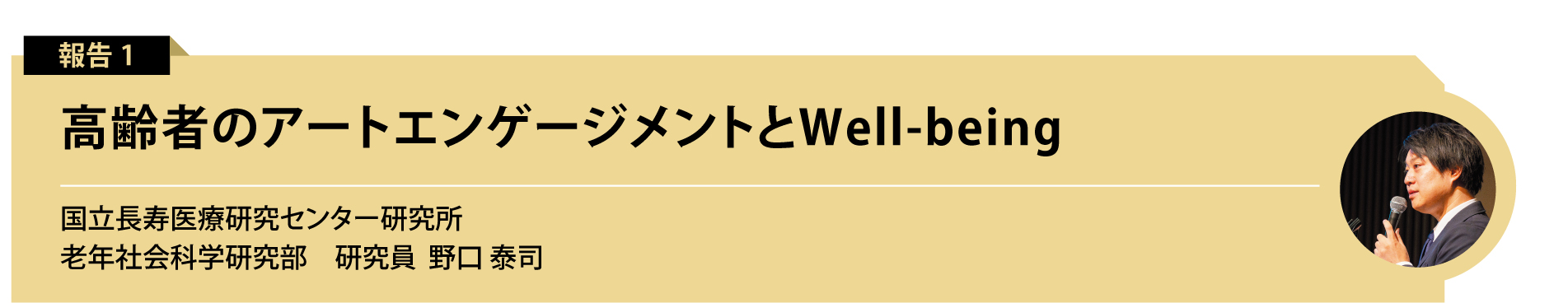
芸術・文化活動が人々の健康や幸福に貢献するというエビデンスが欧州では蓄積されているが、アジアでの報告は少なかった。そこで2022年に愛知県内の公共・民間施設において地域高齢者に対して質問紙調査を実施。その結果、歌唱、絵画、写真撮影など、自らがアートを実施・参加する場合は、その頻度が高いほどウェルビーイング得点が特に高くなると報告された。研究データの介護現場での活かし方についてのコメントを受け、レクリエーションにその要素を入れていく方法などが提案された。
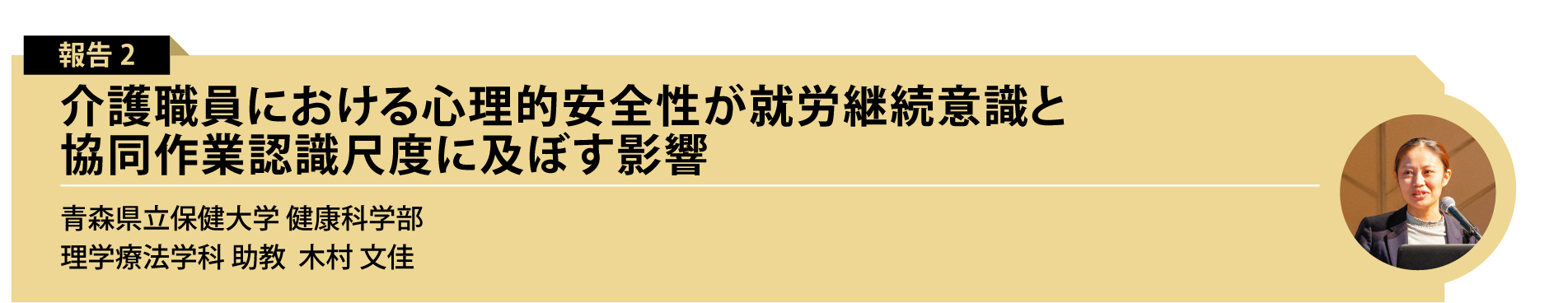
心理的安全性とは職場のような特定の状況下で、対人関係におけるリスクを取っても安全だと思えること。全国老施協所属の施設に協力を依頼した結果、個人が職場に対して心理的安全性を感じていることよりも、目標を据え、チームの協働作業に対する肯定的な認識を醸成する環境を作ることが重要だと報告された。介護職員の定着や就業意識の向上のためには、こうした研究結果を採用にも活かせないかとコメントがあった。
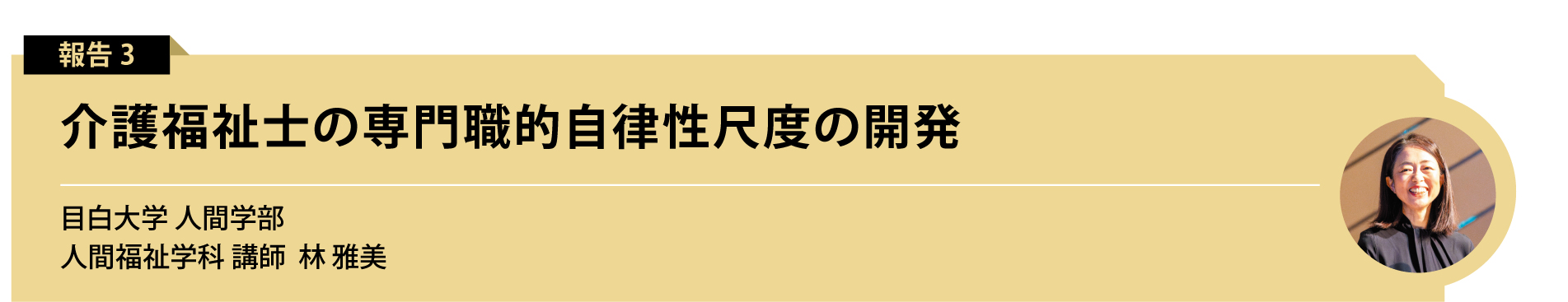
介護福祉士の専門職化を促進するために、インタビュー調査から、「認知力」「洞察力」「情報収集・共有力」「自己啓発力」「実践力」「危険察知力」「自己分析力」と命名した38項目7因子構造からなる尺度を生成。介護福祉士の自立性を評価するために、一定水準の信頼性と妥当性を確保したと報告された。介護福祉士の資格を取ることをゴールとするのではなく、専門性を現場でどう高めていくかという研究も望みたいとコメントがあった。
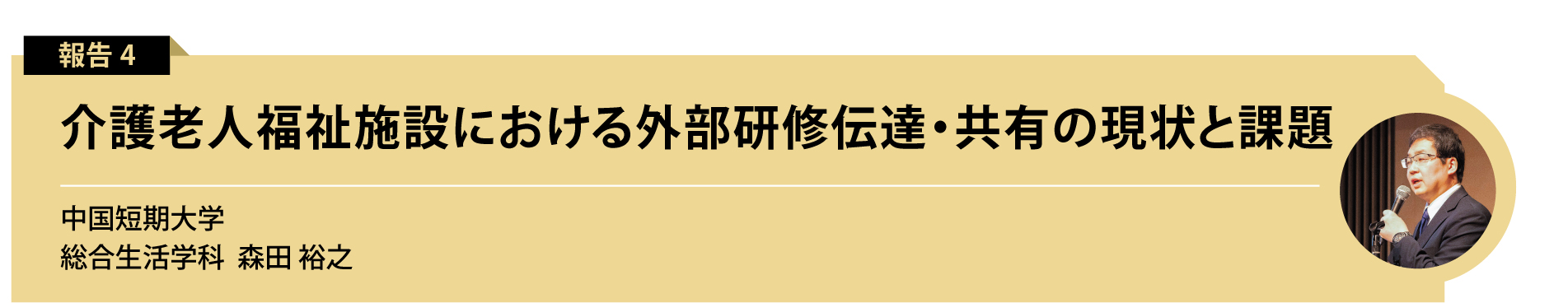
外部研修に派遣される職員は限定されるため、施設のほとんどが施設内での伝達・共有を行っているものの、「職員の時間的余裕がない」「伝達・共有を行うために同じ研修を何度も行う必要がある」「伝達・共有する仕組みが整備されていない」「伝達・共有する職員の能力が不足している」などの声が集められた。より適切な伝達・共有のために、ICTの活用やOJTの仕組みづくりが必要であるとの報告を受け、そのための有効な手引書も考案したいとのコメントがあった。
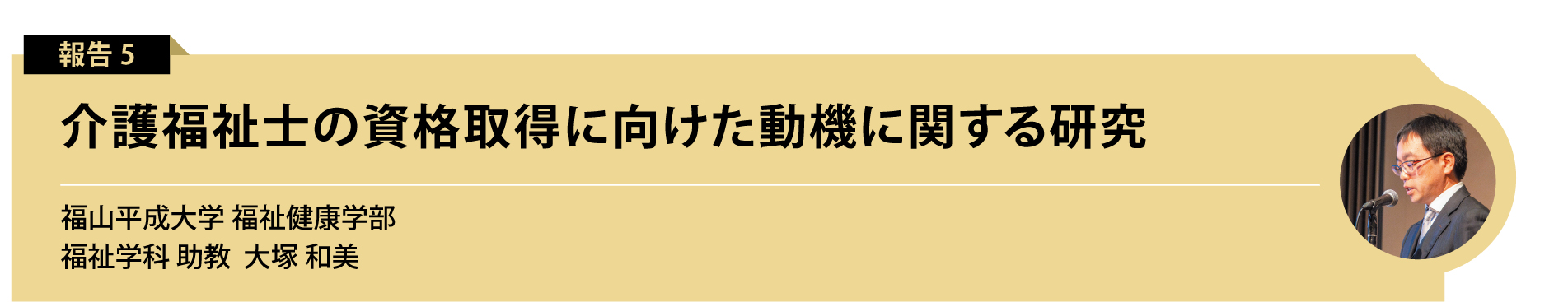
養成校の殆どが定員割れしている状況から、無記名式のウェブアンケートで介護福祉士を調査。介護に興味・関心を抱いた時期は「高等学校」が最も多く、きっかけは「祖父・祖母との同居」、「介護に関する授業を学校で習った」「介護施設の職場体験に参加した」と続いた。資格や仕事に対するイメージは、「専門的な知識や技術を活かすことができる」が最も高かった。こうした研究データをもとに、介護職員の獲得のために働きかけるべきだとコメントがあった。
取材・文=池田佳寿子
