福祉施設SX
大山知子会長と そのだ修光常任理事が語る 介護業界の今、 そして未来のために。 全国老人福祉施設協議会は こう動く!
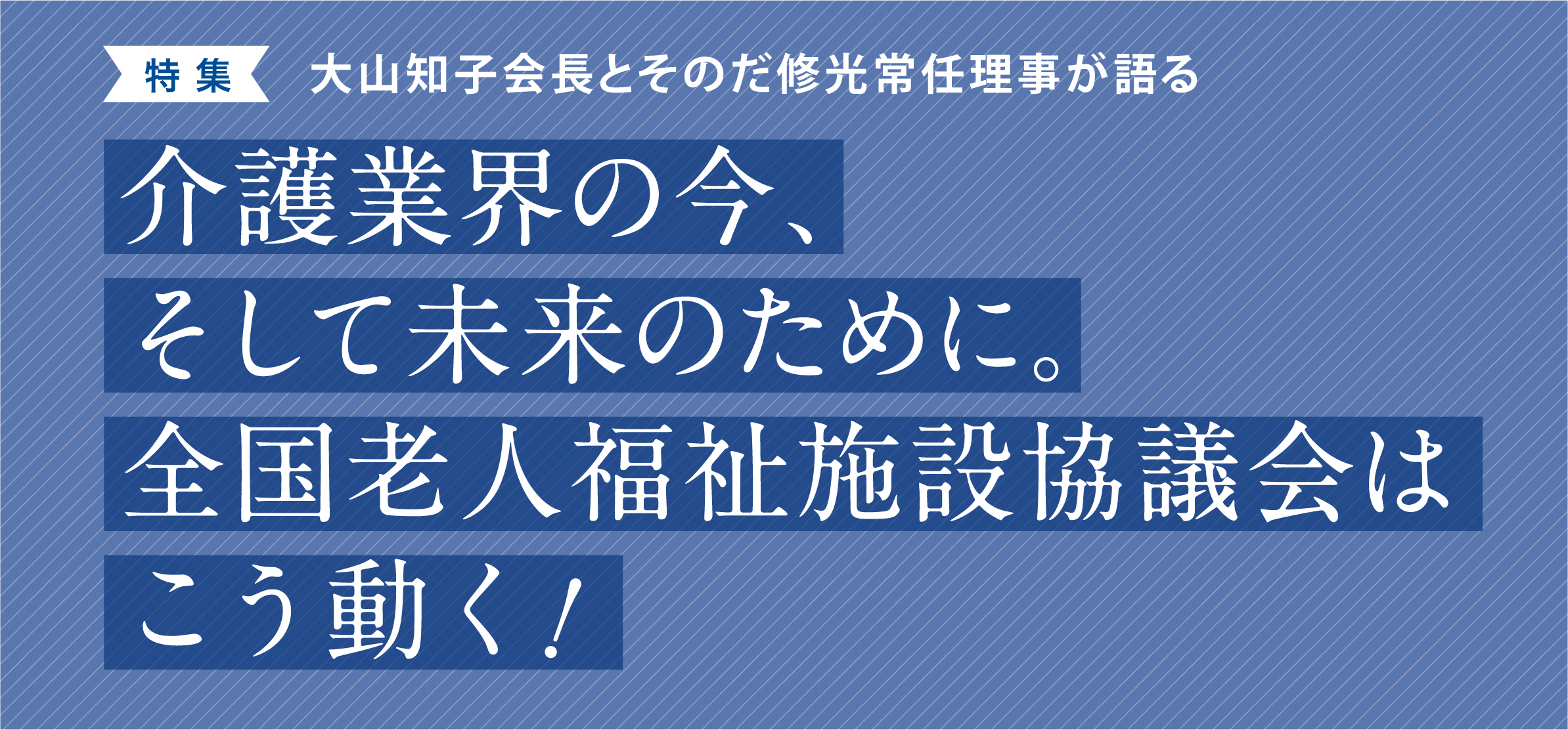
今、介護業界は、かつてないほど多くの問題と向き合っています。 これを打開するためには、 より根本的なところからの変革が必要なのではないでしょうか。 今、私たちにできることは何か。 待ったなしに何を始めなければならないのか。 全国老施協の里村浩常務理事が聞きました。

令和6年報酬改定と今後の見通しについて
社会経済の 変化についていける改定を
里村 令和6年度の報酬改定では大山会長の力強い推進力と、多くの理解ある国会議員に協力をいただき、プラス改定を勝ち取りました。大きな成果だと思います。改めて報酬改定への評価をお聞かせください。
大山 私は強い気持ちで必要なパーセンテージを示したものの、雲行きは怪しくなり、これはマイナスもあり得るのかと失速を感じたときもありました。しかし何としてもマイナスは阻止しなければならない。かつてとは違い、全国老施協内の組織内議員はおりません。これが非常に痛手でした。そこで都道府県・市老施協の皆さんには、それぞれのお膝元の国会議員の先生方に陳情をしていただき、私たちは厚生労働省や国会議員など中央の先生方にアクションを起こすというサンドイッチ方式を初めてやらせていただきました。合わせて300人を超える議員の方と接触することが叶いました。その結果どうなるか心配ではありましたが、プラス改定の1.59%にもっていくことができました。基準費用額を含めれば、実質2.04%相当の増額ですが、その後の物価動向や企業の賃上げ状況、最低賃金が10月から50円以上の引き上げとなることも鑑みると、決して喜べないのが現実です。この改定では、社会経済の変化についていけていません。物価スライド、賃金スライドの要請をしてきましたが、やはりここはしっかりとしたエビデンスをもって、今の状況というものを強く国に訴えていく。それが老施協の今後の仕事だと思っています。
里村 物価スライド・賃金スライド制度の導入は、政治力が大きな決め手になると思いますが、そのだ常任理事はいかがでしょう。
そのだ 我々全国老施協は、厚労省、財務省に大山会長をはじめ役員の皆さんと何回もアクションに行き、その結果がこういう形になりました。いまだ会員の皆さんの状況は厳しいものがありますが、今回の報酬改定については、診療報酬改定率よりも上乗せができました。今まではあり得なかったことで、成果として喜んでよいのではないかと思っています。ただ、これから3年間はこの報酬は変わりません。他産業の皆さんが従業員の給料を上げていくのに、我々の施設はこの3年間同じ給料で行くわけにはいかない。何らかの予算措置をしていただかないと困るということは、私からも厚労省にいわせていただきました。介護の現場だけ賃金はそのまま据え置きでいきなさいなどとはいえないのですから、これからはしっかりと政治の場でも、我々は訴えていかなければならないと考えています。
里村 介護保険制度の制度政策というのは国が決めることなので、やはり国会議員の先生の中に福祉・介護に精通した方が多いほど、政策も違って来ると思いますが、いかがでしょうか。
大山 私どもはそのだ常任理事を前回の参議院選挙で国会議員として再選させることができなかったという非常に悔しい思いがあります。しかし先生が施設の現場で生身で感じていることがたくさんあり、また議員として培ってきた人脈があるので、その中で訴え続けていただいているというのは、陳情などの活動をする上で非常に大きな力になりました。だからこそ、先生に議員バッジをつけていただければ、さらに強固に訴えていただける立場になるだろうと思っています。制度政策は国が決めることなので、そこを踏まえて、私たちの施設が存続するためにはどうしたらよいのか、ということを本誌面を通して介護現場の方々に知っていただくことが重要ではないでしょうか。
里村 社会保障にご理解のある国会議員の先生を一人でも増やしていく活動は絶対に必要ですね。
大山 中でも、介護施設を実際に経営した経験があり、介護の現場について細かな点までご存知で、今までの経緯や流れなども把握している方かどうかは非常に大きなポイントだと思います。
施設経営の将来と2040年問題について
日本経済を支えるインフラとして いかに事業者を存続させるか
里村 先日、社会福祉法人立の鹿児島と沖縄の特養が一カ所ずつ、施設を閉じるという報道を読みました。いずれも人材確保ができないため、そのような選択をしたという記事でした。営利企業であれば赤字なら撤退という選択肢がありますが、やはり社会福祉法人だとそういうわけにはいきません。地域の福祉・介護を守るという使命があるため、これまではそうそうなかったことですが、物価高騰、人材確保困難もあり、今後、こういう事例が増える可能性があります。日本の社会保障はこれからどうなっていくのか、社会保障制度を単に負担と捉えるのか、国民が安心して働くことができ経済成長のために必要なインフラとして捉えるのか、為政者の考え方次第で将来が変わってきます。そういった時代の分岐点に来ているのではないかと思います。
そのだ そもそも介護保険は市町村が保険者です。そして介護を必要とする人たちが市町村のなかにいる。その人たちを介護する場所がなくなるということに対する責任は、社会福祉法人だけが負うべきものではありません。介護を必要とする人たちを守っていくためにはどうあるべきなのかということを、市町村でよく考えなければならないということです。人件費の問題も、物価高騰の問題も、社会福祉法人を経営する皆さんだけで抱えなければならないということではありません。ですから国の制度の中で、市町村という単位で介護保険があるのだということの認識を新たにしてもらわないと困ると思っています。我々全国老施協はみんなでスクラムを組んで、広く現実を知っていただくことや国に対してアクションを起こすことに頑張っていきます。
大山 人手不足は今だけじゃない、ということです。実は最近、介護養成校のブロック大会がありました。その時に伺った話ですが、あるイベントで専門学校の学生が200人以上集まった中で、福祉の専門学校にはたった3人しか来ませんでした。美容関係やペットのトリマーなど、今、旬の仕事の学校には30人近くの学生が列をなしているにも関わらずです。私たちはここ何年も、介護福祉士の魅力というものを訴えながら、興味関心を引き寄せる努力をしてきました。そして、職場として実態を知ってもらいながら、こんな職場なら働きたいと憧れてもらえるような魅力ある施設づくりや施設で働く介護福祉士の魅力を訴えて発信してきたのですけれど、それでもやはり世の中の学生たちの視点というものは、そういうところだけに重きをおいていないということがわかり、これが現実だと思いました。この現実の中で、私たちはどうやって人材不足を解決したらよいのかと思います。もう一ついえば、私たちは介護の質を上げて、地域の皆さん方に選んでいただけるような魅力ある施設づくりをするために非常に努力をしてきました。介護施設が選ばれる時代に入ってきたときに、経営効率も大切ですが、いかに存在価値を高めるかにも注力しました。しかし、今、倒産ということが起きていることを鑑みると、国は〝社会福祉法人は介護の質を上げなさい、そして経営もしっかりとやりなさい〟と、社会福祉法人に委ねるだけになってしまっているのではないでしょうか。そして赤字になったり、人材不足になったりして、クローズになる。この現実も伝えたいです。
そのだ 人手がなければ人手を探して来るのも、市町村の責任だと私は思っています。国も補正予算を組んでしっかりと市町村にそのお金を渡してほしい。人材の流出を防ぐのは国の役割ではないでしょうか。
大山 ここに解決方法を見出さない限りは、経営の維持は非常に難しくなっていく。利用者はいらっしゃるのに、働き手がいないためにクローズするとなったら、その地域の介護サービスが提供できなくなることになって、住民の損失はとても大きいことになります。これは私たちの団体だけで解決できる問題ではなく、本当に日本の人口構造、社会経済の中で、いかに事業所を存続させていくのか。もしくはどのような形で2040年を迎えていくのかということをしっかりと考えていかなければならいないときに来ている、ということですね。
介護に関わる制度の見直しについて
施設管理者・経営者を 疲弊から救うために
里村 予想以上のスピードで少子化が進んでいて、これを回復できたとしても100年はかかるというところまできています。介護業界だけではなく労働人口が減ってきている中で、どうやって介護職員の確保や養成をやっていくべきでしょうか。
大山 介護を小学校の義務教育の授業の一枠にしてはどうでしょうか。福祉というものをしっかりと教育していくことで、効果が出るのではないかと思います。
そのだ 私は2000年の介護保険導入当時、衆議院議員でした。そして3年間、介護保険導入についてなぜ必要なのか、どういう人たちに働いてもらうのか、そしてどうやって地域に貢献するのかが議題となりました。介護保険というのは国民に新たな負担をさせることですから、理由づけがしっかりしていないとできない。そしてこの理由づけが、実は、毎年1兆円ずつ増えていく医療費の伸びをなんとかできないか、ということでした。医療費の伸びの原因となっている高齢者の皆さんの介護の部分を除けば、医療費の伸びをゆるやかにできるので、介護は国民が負担する介護保険料で補えばよいということになったのです。そして、それと同時に各地域では、働き場所ができたと喜んだわけです。企業誘致をしなくても介護の現場で雇用が生まれると。さらにそのときに、介護職員は公務員に準ずるといわれたのです。だから公務員と同じような待遇の介護職員として働けるということになり、どこの高校も専門学校も介護福祉学科をどんどんつくりました。ところが今や、介護専門学校を出てもすぐには資格も取れない、介護士として働きはじめても給料も上がらない、いってみれば、敬遠される仕事になってしまっています。現状を打破するにはさらに一段、給料を上げないとだめです。介護の仕事は苦労もするけど、給料もよいということを示さないと人は来ない、人手は増えないのです。
大山 介護の仕事は社会保障で必要なコストだと国が捉えて、国民も料金が上がっても安心なセーフティネットと捉えるかどうかで大きく違ってきますよね。大変な仕事なのですから、世間一般に足並みを揃えるだけじゃ魅力ある仕事場とは思いづらい。何らかの措置をしてくれない限り解決策はないと思います。
そのだ 社会福祉事業というのは、認可をいただいてやっているのですから、どんな人の介護もしっかりやっていくのが我々の現場です。それはやはり、制度の問題として決着をつけないとならないと思っています。
大山 2000年に社会福祉事業も民間事業との競争の時代に入りました。特養は社会福祉法人でしか認められていませんが、在宅はすべて営利企業との競争になっている。営利企業も以前と比べて倒産が増えていますから、その辺りの整合性も含めて、国は大きく捉えていかないと大変な問題が浮上して来るのではないでしょうか。
そのだ 制度はもう行き詰まりにきています。私は介護保険も医療と同じに考えないとならないと思います。税と保険と一体なのです。保険料も地域によって月額8000円のところもあれば3000円のところもある。住んでいるところでこれだけ介護保険料が違うのはいかがなものか。住んでいるところで格差が生まれるようではだめで、これは調整していかないといけません。
大山 物価高騰の影響も含めて3年に1回の見直しでは間に合わない状況です。今年度の改定では令和8年度については令和6年度の決算の状況を見て令和7年度に考えるといわれましたが、これも不確かな約束ですし、期待はずれになっても困ります。そんな中で各法人が給与の見直しをどのくらいできるかと考えると、もう限界に来ているというわけです。
そのだ だからこそ、声高に国に訴えて、老施協として政策を届けていかないといけない。
大山 その一方で気にかかるのが、経営的状況の厳しさから来る施設のトップや職員さんたちの疲弊度です。頑張ってくれている職員さんたちには、いかに地域にとって必要不可欠な存在であるかを知ってほしい。現場が意気消沈していては、誰も幸せだと感じられなくなるわけです。そこを訴えて、国には待ったなしと感じて動いてほしいと思います。
そのだ 現実問題として制度を変えることはすごく難しい。しかし市町村から国に対して提案すべきだと思います。介護保険があっても、それを使える施設が無くなるということですから、どんどん発信していかないといけない。
大山 私たち社会福祉法人の介護施設は、その地域にあったケアを提供し、特色を出して、介護の質を上げるためにいろいろやっているのにもかかわらず、公定価格のもとで報酬は何も変わらない。せいぜい加算で少し取れるくらいの話ですが、それさえ条件が厳しくて取り切れていない。医療が再編していったように、介護も地域に応じてどのように再編していくべきか議論が必要です。
里村 介護保険制度ができて、25年近くたちますが、少子化がここまで進むとは思わなかったし、長いデフレの後に、インフレがやって来るということも想定していませんでした。社会経済情勢に制度が追いつかず、制度疲労をしていると思います。だから今、もっと具体的な議論を政治の場でしていく必要性を認識される方が増えないといけない。現状維持では明るい将来はこないことを、わかってくれる先生がたくさん出てきてくださるとよいと思って、お話を伺っておりました。

社会保障に見識のある国会議員の必要性
厳しい介護・福祉業界への 理解を得るための活動を
里村 円安と戦争が原因の原材料のコスト高からはじまった物価高騰は、脱デフレへの政策誘導も相まって今後も続くと予想されます。そのコスト増を誰が最終的に負うのか、利用者か、被保険者か、介護事業者か。そのだ先生いかがでしょう。
そのだ 介護施設でどれくらい物価高騰が起き、食材費、人件費、水道光熱費がどのくらい跳ね上がっているかを国が知り、一律に高騰分を分配するルールをつくってもらえないかということを、ずっと自民党の政調や総務会などにお願いをしてきました。しかし地域の財政については市町村が一番よくわかっているからということで叶えられません。理解のある市町村では高騰分を補うものを出してくださるところもあるのですが、理解のないところでは、施設の高騰分の20分の1にも満たないような金額を提示して来るところもあります。介護分としてミシン目を入れて財源を確保してもらえないか、厚労省や財務省、総務省に一生懸命お願いしたことがありますが、そこがうまく伝わっていないような気がして仕方ありません。
大山 交付金の問題ですが、自治体や市町村で格差があり、厳しい自治体では満額ではありません。交付金は交渉したり要望したりしていかないと取れるものではない、という自治体が多い。そこで国に訴えると「それぞれの自治体に予算を出しているのだから、自治体でしっかりやってほしい」となる。ところが自治体首長さんたちの中には、今の介護・福祉の現状の厳しさは喫緊の問題だということを、私たちが要望活動をしない限り気付いていただけない方もいらっしゃる気がします。だから私たちがそこまで運動していかないと、こういうインフレ経済の中では追いつきません。また、養護や軽費老人ホームのように総務省がらみの措置費が今、大変に厳しく、理解も得られにくいということで、全国老施協では力を入れて、自治体へ要望しやすいように雛形を作成し、少しでも現場の皆さんの助けになるようにと考えながら提供しています。しかし、自治体のご理解を得るのはそう簡単ではありません。
そのだ 市町村は監査を行っていますが、監査の段階でも違反を見つけるだけではなく、厳しい状況をちゃんと調査しておかないといけない。経営状態が立ち行かないような状況で、水道光熱費が上がって、給食費が上がり、経営ができないから施設を閉じますとなる前に気づくことが必要なのです。
大山 生産年齢人口も高齢者も2040年をピークにそれ以降はだんだん減って来るわけです。そのシミュレーションの中で、何千人、何万人、2057年で7万人の介護現場の人材が足りなくて必要不可欠になるという数字が出ている。では今、現存している施設のどのくらいが縮小もしくは閉鎖するのかという数字は、全国の人口比から推計して見えなければおかしいのですが、そこを国は明らかにしていません。
そのだ 介護保険をスタートしたときは、これを10年後も使えるということでしたが、実際、10年後は倍になってしまったわけですし、現実は使う人と供給量がどんどん多くなって介護保険料も上がってきた。このように人口統計から考えるシミュレーションも当たらないわけですから、これから高齢者がどのくらい増えて、そのあとどうなるのか、将来をよくよく考えて、設計していかなければいけません。
大山 だからこれは社会保障に理解見識のある国会議員の先生方をさらに増やすべきだと強く思います。
そのだ 会員の皆さんに心配をさせないように、「将来はこうこうなんです」と示していきたいのですが、今の状況ではそれがとてもできない。建て替えをしようか悩んでいる方も多いと思いますが、同規模の建て替えをお金を出してやるだけの意味があるのか。今の100床を50床に小さくまとめていったほうがよいのかという方向性を示すことも全国老施協の仕事だと思います。
大山 私たちは新年度に向けて、社会福祉法人の在り方や進む道、経営の方法についてしっかり論じていかないといけない。倒産しないためにはどうしたらよいのか。厳しいシミュレーションになるかもしれませんが、そこは、私たちはどう生き抜くべきか、ということにメスを入れていかなくてはなりません。
そのだ WAMから建て替えの資金の問題についての話がありましたが、建て替え資金は返済が可能なのかどうか、私たち老施協も会員の現実問題として正面から向き合っていかないといけない。
大山 たとえば合併するといっても、借り入れがたくさんあるところにとっては大変ですから、難しい問題が山積しています。
里村 月刊老施協でも連載をしていますが、建築費の高騰だけでなく、かつてあった施設整備費補助金が昔に比べるべくもなく低水準になっている。すると減価償却費分だけの積立では足りず、建てた際に受けた補助金相当額も自己で用意しないと同じ規模の建て替えができません。縮小も建て替えもできない状況にあっては、財産処分を含め制度を見直してもっと現場で運用しやすく、自治体も動きやすくするようにできないものでしょうか。
そのだ 社会福祉法人はつくるときはいろいろと制約がある。ただ閉じるときにどうするかという話は、今に見合う形で決めておかないとどうしようもなくなります。つくったときの社会福祉法人と今は大きく様変わりしていますから。時代は変わってきています。だから我々全国老施協でしっかり役所に話していかないといけないと思います。
大山 今の時代に合わない制度は少し緩和し、見直しをしていかざるを得ないのではないでしょうか。その結果、社会福祉法人が運営をできるのかどうかを見極める必要があります。

能登半島地震での全国老施協DWATの活動について
大変な状況でも 支援できることが組織の強み
里村 災害が相次いだ石川県の能登半島について、福祉介護ニーズをどうやって復旧、または支えていくか、まずは元日から支援にずっと当たってこられた大山会長からお願いします。
大山 1月1日に起きた地震に対しては、元日から対策本部をすぐに立ち上げて、そこからいかに支援に回るか、現場状況の把握と連動して老施協DWATに登録している職員さんたちにどうお願いして回していくかという作業を、事務局含めてしっかりと動かしていただけたというのは、現場にとっても助かることでした。10月25日現在、全国老施協DWATは102チーム303人を派遣できています。それぞれの自法人さんも厳しい状況の中で協力をいただけているというのは本当に頭が下がる思いです。団体の強みは、こうした災害のときに、同じ施設同士の協力がいかに不可欠であるかを意識している会員さんがいるということであり、全国老施協だからこそできている応援派遣ではないでしょうか。こういう厳しい状況でも支援ができるということが組織の強みだと私は思っております。
里村 実際、7月末の時点でインフラが十分に復旧していませんでした。水道はやっと通ったけれども、下水道は完全ではありません。壊れた家はそのままで、そこで暮らすというのがなかなか厳しいという印象をもちました。それが、せっかく直しているところが大雨でさらわれてしまって、また同じようにトンネルの工事からやり直さなければいけない。相当復旧が遠のいているような心配があります。その辺の思いと全国老施協の立場としてお考えはいかがでしょうか。
大山 能登は特殊な地域です。幹線道路も1本程度しかないところで復旧には時間がかかる。高齢化率が50%。厳しい状況の中で職員さんが戻ってこないわけですね。私はこれを見て、万が一の災害時だからではなく、日本の将来を見ているようだと感じたところがたくさんありました。しかし、そんな社会活動が停止する中でも、利用者のために支援を継続する施設を見て、福祉施設は地域の核であることを確信しました。そういうところも見ながら、行政というのはどうあるべきか、最後に残って支えるのはどこなのかということを改めて訴えるよい時期ではないでしょうか。半年後に巡回したときも、こんなに復旧が遅れている。その中でも施設はしっかりと復旧に向けて仕事をしていらっしゃる。これにはもう感謝するしかありません。そこで働く職員さんたちは、本当に介護という仕事が好きで、利用者のことを大切に思っている人が多いのです。全国の特別養護老人ホーム、養護・軽費も含めた福祉施設の管理者、職員さんたちが、この地でしっかりと生き抜くのだという覚悟を持っているからこそ、災害があっても新たに復興して、しっかりと地域のために存在意義を示していただけている。ここまで民間の社会福祉法人に頼らざるを得ないということを皆さんに自覚していただきたいというのが、私が2回伺った中で、痛切に感じていることです。これは私が代弁していかなければいけないことだと思っております。
里村 会長のご発言の中で、近い将来の日本を見ているようだという言葉もございました。利用者も職員さんも含めてなかなか人が戻ってこないものですから、ニーズがある間は応援派遣を当然続けていくべきだと思っていますが、応援派遣は根本解決にはならず、本来は職員採用の募集に人が応じてくれて、その地域に人が住んで、その地域のお年寄りの介護ケアをしてくれて初めて、復興・復旧となるのではないでしょうか。
そのだ 本当に現地の人たちは大変な苦労だと思いますね。今回の水害もそうです。これまで全国老施協はいろいろと皆さんに協力をしていただき、復興に繋げてきたわけですが、今回は何より、大山会長が災害対策本部を設置して、そして現地に行きましょうということになった。それは能登の皆さんにとって本当にこころ強いことだったと思います。「我々は、全国老施協の会員でよかった」と、今回のこの災害の対応を見て思っているに違いありません。前老健局長の間隆一郎氏(現:年金局 局長)から感謝の電話が来たのを覚えています。そしてDWATも、自分のところも大変で、お手伝いの人を出せるような状態でもないのに、「あそこは我々より大変な状態だから」といって、会員の皆さんのところから派遣している。介護を受けなければならない人たちをしっかり守っていかなければという気持ちは、全国老施協にしかできないと私は思っています。全国老施協は会員のために本当に一生懸命頑張っているということが、一番つぶさにわかったのが今回の能登の災害だったのではないでしょうか。
大山 最近は帰属意識が薄れてきて、団体に加盟しなくても情報はどこからでも入って来るからいいという人もいます。ただし私達の団体の役割は、最新の情報を会員さんに提供することだけではありません。こうした災害のときに同じ施設同士の協力が不可欠であるかを意識していただける会員さんが、どれだけ多くいるかが、団体の価値の一つだと思います。組織が小さい大きいという比較ではありませんけれども、やはり人数が多ければ、その分、派遣できる人数も、そして期間もこれだけ伸びているのだと思います。今回、300人超の方々にご協力いただき、これは本当によそではできない、うちだけの団体の力で、こういう厳しい状況でも、お互いさまという互助の精神で支援ができるということが組織の強みだと私は思っております。気持ちをすぐに行動に移して全国の皆さんにご協力がいただけたからこそ、この支援を継続できました。改めて感謝申し上げます。さて、今回はこうして話し合う中で、多くの課題が浮き彫りになってきましたが、DWATの実績を見てわかるように、全国老施協だからこそできること、動かなければいけないことが、さらに明確になったように思います。今日は本当にありがとうございました。

撮影:柿島達郎/取材・文=池田佳寿子
