福祉施設SX
介護人材の確保と育成に関する 課題と展望 鈴木 俊文教授(静岡県立大学)
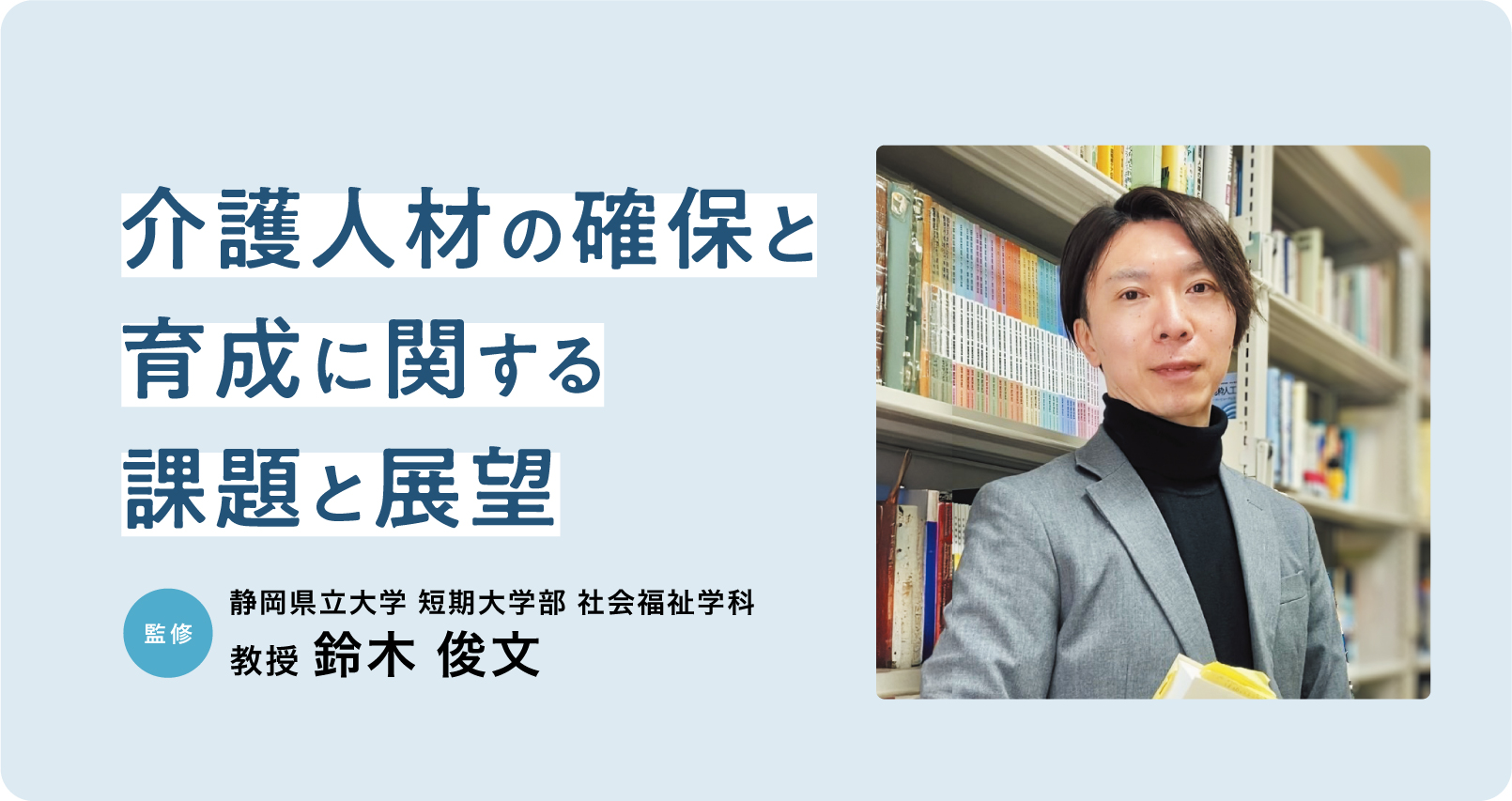
「介護ポジティブ層」を さらに取り込むために
介護に対しては「無関心」「ポジティブ(エッセンシャルワークという認識)」「ネガティブ(きつい)」の3つの反応があり、各々の層に対して異なる切り口の広報戦略が必要になります。一番難しい「無関心」層に対しては、まずは「一般教養」として介護の知識を学んでもらうために、一般大学や高校に施設の職員が出向き、出張講座などを開いて関心層の裾野を広げる努力をするのもよいと考えます。
「ポジティブ」層は、今回の専門学校生のように家庭内での介護経験が契機になるケースが多かったのですが、最近は高校生の例のように「家族など身近な介護職の存在がきっかけになることも増えています。こうした「ポジティブ」層に対しては広報活動が最も有効なので、これから解説する方法を糸口に、「ネガティブ」層も巻き込みつつ働きかけてみてはいかがでしょうか。
介護を広く社会的な文脈で 捉えることが有効
SDGsが広く啓発されたことで、社会貢献や地域連携に関心をもつ若い人が増えています。今回の高校生のインタビューにもあるように、今の学生たちは「地域活動」というキーワードに関心が高く、介護職を地域と連携した福祉活動の一環として捉える傾向があります。折しも2040年に向けて高齢者人口が減少し、地域間のニーズの格差が生じはじめています。また近年では、 介護施設の役割として、新たに福祉避難所など地域共生の視点が求められています。
こうした社会福祉法人の公益的な取り組みは、人材確保の戦略としては追い風になります。これからは人材確保の点からも地域単位での協働関係、連携組織が非常に重要で、一方の人材側から見たキャリアモデルでも、従来の制度サービス内の役割だけでなく、災害時の活動や地域活動も含めた多様なルートが構築されることは歓迎されます。
現在、国では介護人材の役割とそのキャリアの多様性を表す「山脈型」のキャリアモデルを検討しています。このモデルは、介護人材構造における中核的介護人材の位置づけや役割を捉えていくうえで非常に重要な視点で、今回のインタビューでも、高校生が「さまざまな介護施設で働いてみたい」と語っていることに、多様なキャリアプランへのニーズの兆しが感じられます。この「山脈型」キャリアモデルは、厚生労働省の「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会 でも議論されている重要なテーマで、介護人材確保と育成双方の土台として、今後さらに議論が進められていくことでしょう。
介護職を知ってもらうために
1. 既存のネットワークを活用した 介護体験への参加促進
現代の多くの学生は「心理的安全性が高い状態」で活動に参加したいという傾向をもっています。そこで学校のクラブ活動や地域のスポーツチームなど、つながりの強い仲間と一緒に介護体験に参加するチャンスを生み出すことが、若者が福祉活動に関わるきっかけをつくりやすくなるのではないでしょうか。「介護」をキーワードに新たな「つながり」を構築するよりも、既存のコミュニティーネットワークを活用して、そこに介護・福祉の要素を混ぜていく方法が現代に適していると考えます。
2. ご利用者としっかりと関われる実習体験
介護福祉士養成課程では2年生になると介護計画の立案・実施・評価というPDCAサイクルを学ぶ実習が重要になり、「介護過程」を学ぶために、ご利用者とコミュニケーションし、生活状況の観察をすることを真剣に求めるようになります。高校生のインタビューでも、実習におけるご利用者の存在の重要性に気づき、ご利用者との距離を重視している発言があったことは興味深く、実習経験を通して彼らの介護福祉観が醸成されていることは確かで、こうしたニーズをいかに満たし、サポートできるかどうかが、介護実習に参加した学生を就職に結びつけるための大事な要素になります。
現在は介護現場での教育文化が醸成されていて、実習生の受け入れ希望は多くなっていますが、実習の質を高めるために養成校の教育内容と現場での実践をうまく橋渡しすることも課題となります。さらに心理的安全性を確保することは、学生が介護施設での実習や就職を検討する際にも重要な要素になっています。
また外国人の実習生に対してはマニュアル化を進めるだけでなく、文化的理解を深める対話が重要で、外国人実習生に学んでもらうだけでなく、施設側も相手の文化や言語を学ぶ姿勢をもつことが必要になります。
3. ホームページなどでの 施設の理念の表明
就職先を選ぶのに際して、現場での実習経験等の有無は重要な要素にはなりますが、単に実習などを経験してもらえば、それが即、進路選択の決め手になるわけではありません。
多くの学生・生徒は、施設がどんな使命感をもって社会のなかでの役割を担おうとしているのかを、あらかじめホームページなどで調べています。実習や見学に来たとしても、そもそもその施設に関心をもって実習や見学先として選んだかどうかが重要なのです。
介護福祉士養成校の学生や福祉を目指す高校生は、理念や人の尊厳といった高いレベルの視点をもっていることが多いので、介護施設の理念は非常に重要であり、学生や生徒、さらには既卒の求職者が施設を選ぶ際の重要な判断基準となっています。多様性の時代において、施設が自分たちの理念や目指すものを明確に示すことは重要な広報戦略となり得るのです。

取材=池田佳寿子
