福祉施設SX
多角的に取り組む排泄ケア PART3-1 排泄ケアに取り組むベンチャー企業に聞く 先進技術はどこまで業務負担を軽減できるか?
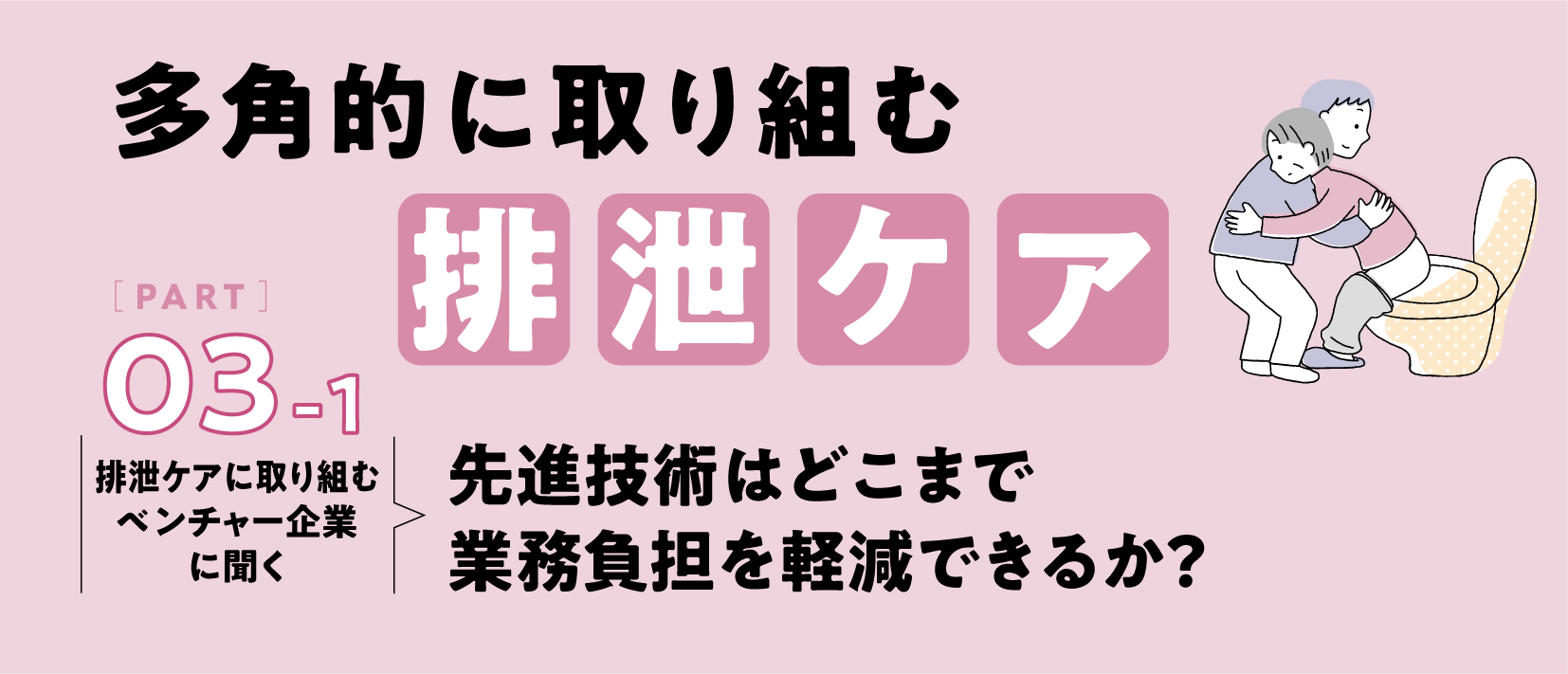
2017年から現在まで5世代にわたって段階的に改良を重ね、無線化、小型軽量化、充電時間の短縮に成功。排便を検知する便汚染予防デバイスの開発にも成功。

超音波センサーで尿のたまり具合を見える化
排泄の失敗を減らしたい それは人としての尊厳を守ること
自身の失禁体験をきっかけに、誰もが、何歳になってもトイレの悩みから解放されるようにと考え、アメリカ留学中の2013年に、排泄予測デバイス事業を立ち上げました。
作ったのは小型の超音波センサーをご利用者様のお腹に貼り付けることで、尿のたまり具合をリアルタイムでモニターに表示する機器。膀胱内の尿のたまり具合や前回の排尿時刻、これまでの排尿履歴などでその方の排泄傾向を把握したり、「そろそろ通知」や「でたかも通知」などのお知らせ機能を活用することで、漏れの悩みやパッドの無駄を減らします。複数のご利用者様の排尿予測を一つの画面で一括管理することも可能です。
この機器が役立つのは、業務やコストの負担軽減のためだけではありません。排尿を予測することで、トイレ誘導がしやすくなったり、個別ケアの実践にもつなげたいと考えました。そのため社内にカスタマーサクセスチームと呼ばれる専門職を配置。その名のとおり、顧客である介護者の方々にサービスを超えた、排泄ケアの「成功体験」をお届けすることが目的で、カスタマーサクセス職はそのためのサポートを徹底的に行います。

介護者と共に排泄ケアの 課題解決や成功体験を目指す
看護師や介護福祉士の資格をもつスタッフが自社の排尿予測デバイスを活用して、介護施設など導入先の課題解決や機器の適切な使用方法まで、総合的にサポートするのがカスタマーサクセスチームの仕事で、これまでに約1,000施設で実績を積んでいます。
アセスメント重視のアプローチをしているので、通知機能を活用するだけではありません。1〜2週間のデータ収集により排泄パターンを分析し、根本的な課題解決策を提案する仕組みになっています。
排泄予測センサーの導入により、従来の機械的な流れ作業から脱却し、個人の排泄パターンに合わせたタイミングでケアを行うことで成功率が50%程度向上し、職員のやりがいも高まり、職員が排泄ケアに前向きに取り組むようになったというお声も数多くありました。またオムツ代の削減効果が顕著で、特養などでは40%の費用削減を実現した実績があります。
自社の製品のおかげで、介護する方とされる方、そして私たちも一緒に成功体験を共有できることが、一番のやりがいになっています。
取材・文=池田佳寿子
