福祉施設SX
第3回 全国老人福祉施設大会・研究会議 JSフェスティバル 誌上レポート④ 特別記念プログラム

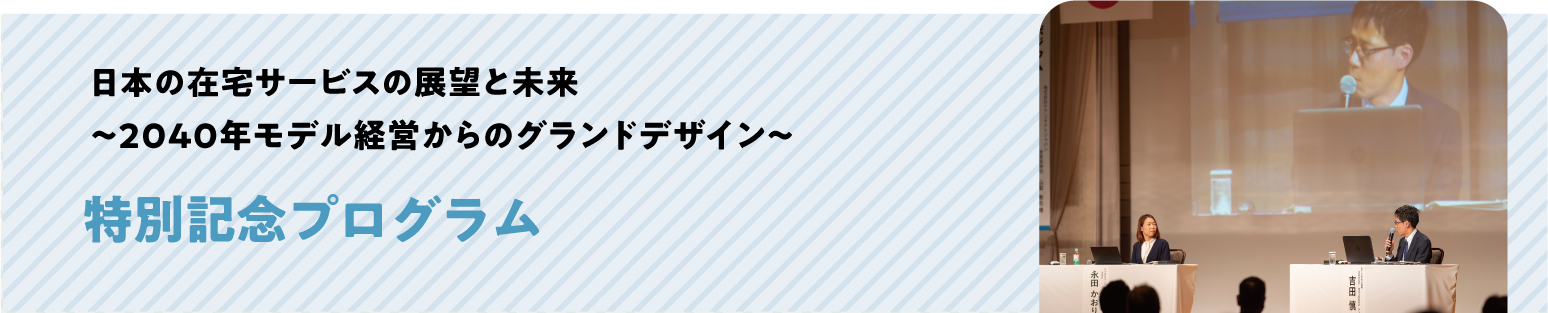
事例をヒントに考える、 在宅サービスの生き残り戦略
介護と看護を連携し、酸素カテーテルの処置も可能な体制を整えている社会福祉法人ひだまり。障害支援では「医療ケアが必要な障害者の短期入所など、ニーズに応じた支援を行っている」と話し、また、出前講座や福祉事業への派遣、保護猫団体と協力するなど、地域福祉の向上を目指す取組を行っていることを紹介。こうした支援を実現するには、「現場で働く人々の質の向上が不可欠。そのために、無資格からフルサポートをして介護福祉士の資格を取っていただく仕組みをつくりました。ほかに選べる夜勤、オーダーメイドシフト、法人内副業、週休2日と3日の選択、5連休取得手当などにより有給消化率は、約80%まで向上しました」。働きがいと働きやすさは表裏一体だと語る永田氏。働きがいの仕組みとして、リーダー以上で実施する経営の勉強会も始めていることを紹介されました。
開口一番「介護人材難と経営悪化によって地方で介護崩壊が始まっている今、いずれ全国各地で同時多発的に崩壊が広がっていく恐れがある」と問題提起をした全国老施協の波潟氏。介護崩壊を抑制する政策の第一は“人”だとし、「賃上げ5%を目標とした処遇改善が必要では」と提起しました。また、「外国人材の平均就労率を30%程度に上げ、通所・訪問を組み合わせた複合型サービスの統合化も重要」と語り、過疎地方については複合型サービスの定員上限の緩和、例えば過疎地での地域特性に応じた基準見直しなどの柔軟性が必要だと訴えました。

シンポジウムの最後に厚労省の吉田氏は「現場で働く人の環境を整えることが、地域共生社会の実現につながることが印象に残った」と感想を述べ、「2024年度の制度改定で成立できなかった複合型サービスについて、今日の内容をもとに改めて提案していきたい」と語りました。
また司会の内藤氏は、本日のまとめとして「地域共生を実現するために、地域全体でどのように支援を行うかが、今日の議論の重要なポイント。そのなかで他産業に勝つという課題がつきつけられた」と締めくくりました。

撮影=本田真康 取材・文=池田佳寿子
今回のテーマは「介護最前線の変革と戦略
〜自ら動く、ともに動く、働き甲斐のある現場への挑戦」〜
